
35歳定年説は本当か?40代以降でも第一線で活躍できる2つの理由
IT業界で35歳定年説というものを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
35歳で定年なんて早いと思いますが、IT業界では実際に35歳定年説というものが存在しています。
近年では40歳定年説なども出てきており、少しは長く働ける業界になってきていますが、40代以降で活躍している人は他業界に比べて少ないです。
今回は、なぜIT業界が35歳定年説と呼ばれるようになったのか、どんなエンジニアが定年まで働いているかについて説明致します。
目次
1.35歳定年説は本当か?
35歳定年説と言われているIT業界ですが、実際は35歳以上も活躍しているエンジニアが多数います。
過去は35歳をすぎると、手が遅い、扱いづらいといった理由で次の現場が見つからないことが非常に多くありました。
ですが、IT人材不足の影響で35歳までと制限していてはプロジェクトが回らなくなり、現在では40代のエンジニアも数多く活躍しています。それによって、35歳定年説ではなく、40歳、45歳定年説などが新しく出てきています。
1-1.30代のエンジニアはどのIT企業でも欲しい人材
前述致しましたが、近年はIT人材不足が大きな問題になっているため、手が動き、幅広い知識をもった30代のエンジニアはどのIT企業でも欲しい人材となっています。
そんな中で案件の募集をする際に35歳といった年齢制限を設けていれば、人材は全く集まらないでしょう。
そのため、40代のエンジニアが活躍できる場が増えてきています。
1-2.コミュニケーション力の高い40代エンジニアが増えてきた
近年では過去のプログラミングだけを黙々と行うような現場はかなり少なくなり、チーム間でのコミュニケーションを取りながらの業務が必要になってきました。
20代にそのような環境の現場で働いていたコミュニケーション力があり、現場の技術もしっかり持っている40代のエンジニアが今も幅広く活躍しています。
上記理由からIT業界の35歳定年説自体はほとんど無くなり、40代エンジニアが活躍できる業界になってきています。
関連記事2.35歳定年説が生まれた3つの理由
冒頭でも述べましたがIT業界では35歳定年説がありした。
その大きな理由は下記3つです。
- 30代のPMが多いため年上のエンジニアは扱いづらいと思われている
- 若者の方が新技術に対するキャッチアップが早い
- 30代後半に技術部門から管理部門へスキルチェンジする人が多い
なぜIT業界には35歳定年説が生まれたのかについて解説していきます。
2-1.30代のPMが多いため年上のエンジニアは扱いづらいと思われている
一次請けの大手SIerからPMとしてプロジェクトに入るのが経験年数も豊富で、昔のシステムも今のシステムも知っている30代のエンジニアになります。
そこから人を集める際に自分よりも年上のエンジニアを使いたくないという理由で下請け業者に「30代まで」といった年齢制を設けているのが35歳定年説と呼ばれる大きな原因です。
使いたくない理由は様々ですが大きくは下記になるでしょう。
- そもそも自分より年上の人に指示を出したくない
- 昔のやり方を押し付けてくる
- 若手に比べて新しい技術、製品の覚えが悪い
- 手が動かない
- 頑固で若手と協調できないイメージが強い
- これからIT業界を引っ張っていく若手を育てたい
IT業界はゼネコンと同じく多重請負型になっているのでトップにいるPMが30代であれば年齢制限が設けられ、40代、50代のエンジニアがプロジェクトに参加するのは難しくなっています。
実際に40代以降のエンジニアは頑固でクセの強い人は多いですが、長年IT業界でシステムを構築、開発してきた経験があるにも関わらず、その人達を活かしきれていないのが現状です。
2-2.若者の方が新技術に対するキャッチアップが早い
IT業界は新しい技術が日々生まれています。それらの新しい技術に対するキャッチアップのスピードはどうしても若手のほうが早く、40代が追いつくには相当の労力が必要になります。
また、他の業種と違い最初に学んだ技術で定年まで働き続けるのは非常に厳しく、同じ言語でもアップデートによって仕様が変わってしまったり、そもそもその言語自体の使用が無くなっていったりします。
そのような業界の中で40代、50代が若手よりもすばやく対応していくのは非常に難しいと考えられています。
2-3.30代後半に技術部門から管理部門へスキルチェンジする人が多い
これはスキルアップとも取られていますが、30代後半になるとPM、PLのような管理職へスキルチェンジを考える時期になります。これがエンジニアとしての35歳定年説と捉えられています。
管理職は現場での作業がメインではなくプロジェクトの管理がメインになります。
一般的にはスキルアップになりますが、エンジニアの場合は現場に残って更にスキルアップしていきたいと考える方が多いですが、企業としても管理職になっていくほうが単金が上がるため、スキルアップを勧めます。また、スペシャリストとして現場に残るためには新しい技術を20代よりも早く身に着けなければならないため、管理職としてではなくスペシャリストとして現場に残り続けるのは難しい業界です。
3.60歳まで働けるエンジニアになるための方法
60歳まで働けるエンジニアになるためには日々の自己研鑽とスタンスを変えることが重要です。
3-1.日々の自己研鑽
まず挙げられるのが日々の自己研鑽です。
ITエンジニアは専門職です。40代の野球選手が日々、トレーニングを行うのと同じようにITエンジニアも日々新しくなる技術の勉強をすることが大切です。
IT業界は他の業界に比べて進化スピードが早いため、常にトレンドに敏感になり、新しい技術も積極的に勉強していかなければなりません。特に若手はITが身近にあるため新しい技術の取得は早いでしょう。20代に負けないためにも自ら積極的に勉強することが大切です。
また、資格を取得してくことも非常に重要です。
20年間、IT業界での経験があるといっても、資格が一つも無ければ今まで自己研鑽を全くしてこなかったと思われてしまいます。例えば現場で新しい技術を使うとなった際に、資格が一つも無いとこの人はキャッチアップしていけるのかとPMから思われ、今までの経験も無駄になってしまいます。
長くIT業界で働いていくために日々、研鑽していきましょう。
関連記事3-2.自分のスタンスを変える
次に大切なのは自分のスタンスを変えることです。
スタンスに関しては下記んの記事にて詳しく記載しています。
関連記事40代になって新しい現場に入ると自分よりも若い30代がPMを行っていることも多いでしょう。
そのPMに対して経験が長いという理由で自分の仕事の進め方を押し付けたり、言うことを聞かなかったりしていては活躍できないのは当たり前です。
PMが自分より若いという理由で依頼された仕事をただこなすだけでなく、経験を生かした30代ではなかなか育っていない観点(障害が起きそうな予感、炎上しそうな設計の仕方など)からアドバイスを行いましょう。
2章でも述べましたが、40代のエンジニアは過去の現場のやり方を押し付けてくる、言うことを聞かない、頑固といったイメージが定着してしまっているため、30代のPMから扱いづらいと思われていることが多いです。
環境を理由にせず、まずは自分のスタンスを変えて取り組むことをオススメ致します。
関連記事4.実際に60歳まで働いている弊社エンジニアの事例
実際に定年まで働いているエンジニアは多数います。私の会社では60歳以降でも活躍している人何人かいます。その一人は、現場で今までの経験を生かしてPMOとして参画し、お客さまからも良い評価を頂いております。
実際に手を動かす立場ではないですが、自社の社員でチーム体制をつくり、新人にも業務を教えています。また、長い経験を生かし、お客さまへの調整を確実に行うのでお客さまからも信頼して業務を任されています。
上記は一例ですが、40代以降でも活躍している人は他にも沢山います。
50代、60代まで活躍できるかどうかは自分次第です。ですが、60代まで活躍するためにはそれ相応の努力は必要でしょう。
5.さいごに
35歳定年説自体は無くなり活躍できる幅が広がってきていますが、まだまだ年齢が上がるにつれて活躍するのが難しい業界になっています。
実際に大手SI企業の一部においても50歳を過ぎ、60歳に近づくにつれて、もらえる退職金が年々減っていくという退職金規定を設けている企業も散見されます。
大手SI企業がそのような状態のIT業界ですので現場で40歳定年説が出てくるのも不思議ではありません。
定年まで働くためには、どの企業に就職するかも大きな要素の一つになるでしょうが、60歳までITエンジニアとして働き続けるには日々の自己研鑽とスタンスを変えることが非常に大切です。若手に負けず、活躍できるようなエンジニアになっていきましょう。
関連記事 関連記事 関連記事
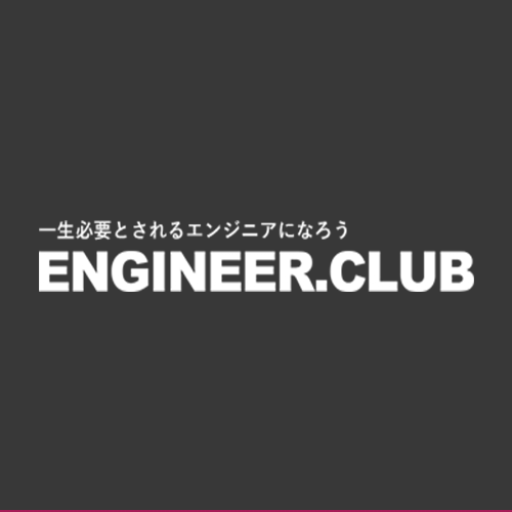









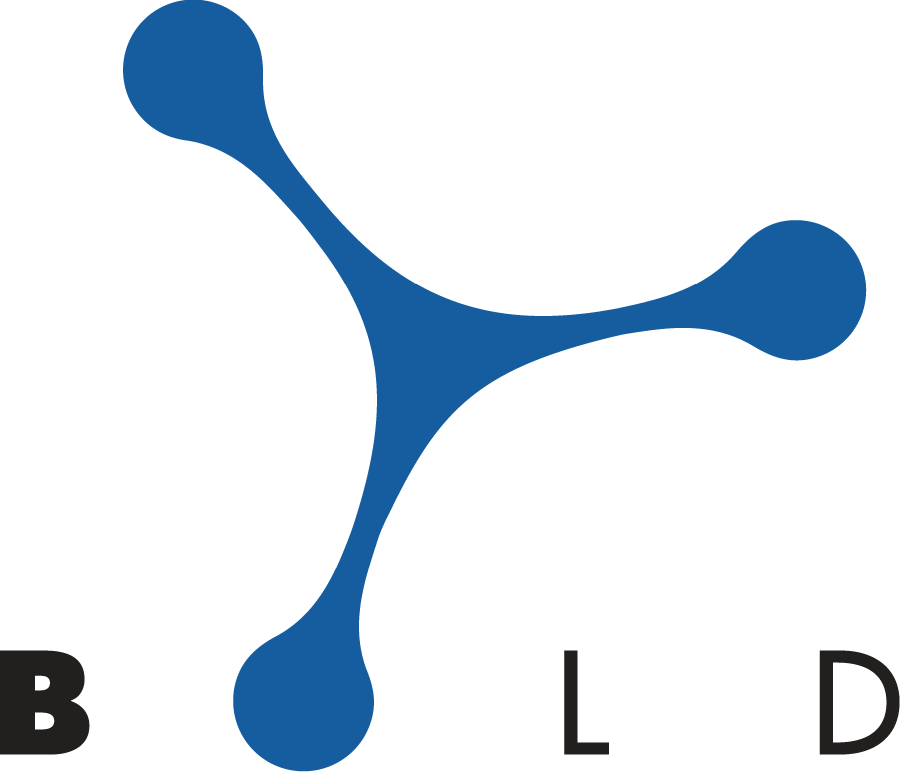
コメント