
LPICレベル1とは?取得のメリットや難易度、合格に向けた勉強方法
LPICは「Linux技術者認定試験」(Linux Professional Institute Certification)の略称で、NPO法人Linux技術者認定機関のLPIが実施するLinuxエンジニアとしての技術力を認定する資格です。
LPICはレベル1から3まで3段階に分かれており、本記事で紹介するLPICレベル1は初級レベルに位置付けられています。筆者が実際にLPIC レベル1を受験した体感としてはきちんと対策できれば決して難しくないですが、現役の方でも対策をしないで受験すると落ちる可能性があるなと思いました。ですので、これから受験をしようと考えている方向けに、本記事ではLPIC レベル1を取得できた対策方法や試験申し込みについてもご紹介したいと思います。
目次
1.LPIC レベル1 (LPIC-1)とは
LPIC レベル1 (LPIC-1)とはレベル1からレベル3の3段階に分かれているLPIC認定資格の中でLinuxについての基本的なコマンドや仕組みについての知識を証明する資格になります。LPICのレベル1には、101と102の2種類の試験があり、両方を取得することでLPIC レベル1を取得したことになります。
1-1.試験概要
LPIC レベル1では、Linuxの基本的なシステムのアーキテクチャを知り、ファイルアクセスとセキュリティ設定、ネットワーキングの基礎などの知識が問われます。
以下に試験情報についてまとめました。なお、101と102の2つの試験を同時に受験する必要はなく、分けて受験することも可能です。特別な理由がない限りは別々に受験することをおすすめします。
- 試験名:LPIC-1 101(101-500: LPIC-1 – Exam 101 (part 1 of 2), version 5.0)
LPIC-1 102(102-500: LPIC-1 – Exam 102 (part 2 of 2), version 5.0) - 試験日程:通年
- 試験方式:パソコンで実施するCBT方式の試験
- 試験時間:101,102共に90分
- 問題数:101,102共に60問(択一選択問題、複数選択問題、入力式問題)
- 合格点数:101,102共に500/800
- 受験料 : ¥15000(税抜)
- 試験内容の概要:以下version5.0の内容になります。
①LPIC101
- 主題101: 「システムアーキテクチャ」
- 主題102: 「Linuxのインストールとパッケージ管理」
- 主題103: 「GNUとUnixコマンド」
- 主題104: 「デバイス、Linuxファイルシステム、ファイルシステム階層標準」
②LPIC102
- 主題105: 「シェル、スクリプト、およびデータ管理」
- 主題106: 「インターフェイスとデスクトップ」
- 主題107: 「管理タスク業務」
- 主題108: 「必須システムサービス」
- 主題109: 「ネットワーキングの基礎」
- 主題110: 「セキュリティ」
1-2.LPIC レベル1 (LPIC-1)で得られる知識
前述の通り、LPI認定試験はレベル1からレベル3まで3段階に分かれており、そのLPI認定試験の中でLinuxについての基本的なコマンドや仕組みなどの知識を問われるのがLPIC-1になります。以下の表でLPIC-1の主題ごとに得られる知識(出題内容)についてまとめました。
| LPIC101 | 主題101:「システムアーキテクチャ」 | ハードウェア設定の決定と設定方法 |
| システムが起動するまでの流れ | ||
| システムが起動し、Linuxが起動する仕組み | ||
| 主題102:「Linuxのインストールとパッケージ管理」 | ハードディスクのレイアウト設計 | |
| ブートローダのインストール方法 | ||
| 共有ライブラリの管理方法 | ||
| パッケージ管理ツールと管理コマンド | ||
| 仮想環境でのゲストOSとしてのLinux | ||
| 主題103:「GNUとUnixコマンド」 | コマンドライン操作の仕組み(シェル、環境変数など) | |
| ファイル管理コマンド(cp、rm、touch、mvコマンドなど) | ||
| フィルタを使用したテキストストリームの処理方法 | ||
| パイプ、リダイレクト処理方法 | ||
| プロセスの生成、監視、終了方法 | ||
| プロセス実行の優先順位変更方法 | ||
| 正規表現を用いたファイル検索方法 | ||
| ファイルの基本的な編集方法(viコマンド) | ||
| 主題104:「デバイス、Linuxファイルシステム、ファイルシステム階層標準」 | パーティションとファイルシステムの作成方法 | |
| ファイルシステムの整合性を維持する方法 | ||
| ファイルシステムのマウントとアンマウント方法 | ||
| ファイルのパーミッションと所有権の管理方法 | ||
| ハードリンクとシンボリックリンクの作成方法 | ||
| システムファイルを検索し、ファイルを正しい場所に配置する方法 | ||
| LPIC102 | 主題105:「シェル、スクリプト、およびデータ管理」 | シェル環境のカスタマイズ方法 |
| スクリプトのカスタマイズ方法 | ||
| 主題106:「インターフェイスとデスクトップ」 | X11のインストールと設定方法 | |
| グラフィカルデスクトップについて | ||
| アクセシビリティについて | ||
| 主題107:「管理タスク業務」 | ユーザ、グループアカウントと関連するシステムファイルの管理方法 | |
| ジョブのスケジュール設定方法 | ||
| ローカリゼーションと国際化について | ||
| 主題108:「必須システムサービス」 | システム時刻を更新する方法 | |
| システムロギングについて | ||
| メール転送エージェントの基礎知識 | ||
| プリンタの管理と印刷方法 | ||
| 主題109:「ネットワーキングの基礎」 | インターネットプロトコルの基礎知識 | |
| 固定ネットワーク構成 | ||
| 基本的なネットワークのトラブルシューティング | ||
| クライアント側のDNSの設定方法 | ||
| 主題110:「セキュリティ」 | セキュリティ管理タスクの実行方法 | |
| セットアップホストセキュリティ | ||
| 暗号化によるデータの保護方法 |
1-3.LPICレベル1取得のメリット
LPI資格を取得するメリットとして転職や就職の武器になることや学習した成果物としてアピールするなど色々あると思いますが筆者が考えるLPIC取得のメリットが以下の2つになります。
①Linuxの基礎的な知識が身につく
LPICレベル1ではLinuxの基礎コマンドが出題範囲に入っており、業務でも使う場面が多い印象があります。LPICレベル1を取得することでLinux環境での作業をより効率的に行い、現場での更なる活躍が見込めるのではないでしょうか?
②LPI資格をセルフブランディングの材料にして、挑戦の機会を増やせる
LPI資格はLinux領域の新たな挑戦権を得るための手段として代表的なものではないでしょうか?なぜなら、求人サイトや案件募集サイトの「必須条件」や「歓迎条件」にLPIC-1を掲げている企業は少なくありませんので、LPIC-1は知識レベルが相手に伝わりやすく新たな挑戦権を得るアドバンテージになると思っています。そして、LPIC-1の学習で得た知識と技術(実務)を合わせてエンジニアとしてのバリューを相乗して高めるのがセルフブランディングの理想的なアプローチではないでしょうか?
2.使用教材と学習方法
筆者は参考書でインプットを行い、後述のPing-tという問題集や実際にコマンドを打ってみて理解度を深めてLPIC101は680点、LPIC102は660点で合格できました。具体的な学習方法は以下の①、②のサイクルを回しておりました。
①参考書でインプット
- 1周目のサイクルでは概要を把握するためさらりと読むだけでOK
- 2周目以降のサイクルではPing-tで間違えた箇所や記憶が曖昧な箇所の振り返りに用いる。
②Ping-tや実習環境で実際に手を動かしてアウトプット
学習時間としては1日3〜4時間を1ヶ月でトータル130時間程LPICレベル1の学習に割きました。(101:15日間、102:10日間)以下で学習に用いた教材のご紹介をします。
2-1.問題集(Ping-t)
Ping-tを一言で言えば、LPICやCCNAなどのIT試験の問題をコンテンツとして提供する学習サイトです。以下のリンクのサイトになります。Ping-tでLPIC101の問題は無料で利用できますが、LPIC102の問題は有料となっています。有料プランは月単位で利用でき、有料期間中は全ての有料コンテンツを利用できます。学習方法としては正解の理由はもちろん、他の選択肢の何が違うのかわかるようになるまで解き続ける方法がオススメです。ただ、本番で同じ問題は出ないので、問題自体を覚えてしまわないように注意しましょう。
Ping-t
2-2.参考書(Linux教科書 LPICレベル1 Version5.0対応)
筆者がコマンドやオプションを把握するインプット材料として参考にしていたのは以下リンクの参考書です。よく「小豆本」と呼ばれており、基礎から学ぶにはうってつけだと思います。本書の付録ではLinux実習環境の使い方も用意してあり、筆者はその実習環境でアウトプットすることで理解を深める学習方法を実践しておりました。また、「スピマス」と呼ばれる問題集も合格者からの評判がいいので前項のPing-tの代わりとして利用してみても良いかもしれません。
Linux教科書 LPICレベル1 Version5.0対応
Linux教科書 LPICレベル1 スピードマスター問題集 Version5.0対応
3.申込みから受験終了までの流れ
3-1.受験に必要なアカウントを発行する
LPICの受験にはLPICの主催団体であるLPIのアカウントと、テストセンターの運営団体であるピアソンVUEのアカウントがそれぞれ必要です。過去にピアソンVUEのテストセンターでLPICとは別の試験の受験経験があるなら、その際に作成したピアソンVUEアカウントを使用できます。ピアソンVUEのアカウント作成は時間がかかるため、作成する場合は早めに以下のリンクから作成を行いましょう。
LPI登録URL
ピアソンVUE登録URL
3-2.試験を予約する
以下の順に従って試験を予約しましょう。
- https://www.pearsonvue.co.jp/Clients/LPI.aspxにアクセスしてサインインする
- [試験を表示]を押下し、LPI試験の中から受験する試験を選択する。
※オンライン受験の場合は「OnVUE Online Exam」を選択してください。 - ピアソンVUE のガイダンスに従って入力していきます。バウチャーを用意しているのであれば「支払い情報と請求情報を入力」画面で忘れず入力し、予約をします。
※バウチャー・プロモーションコードについては「Ping-t」や「学易」というサイトなどでも販売しているので少しでも安く受験したいという方はチェックしてみると良いでしょう。
学易URL
※予約変更やキャンセルの方法は予約完了メールに記載されているのでチェックするようにしましょう。
3-3.受験する
受験方法によって流れが変わってくるためテストセンター受験とオンライン受験を分けてご紹介します。
3-3-1.テストセンターで受験する場合
・受験前
試験会場には時間に余裕をもって、15分前には着くようにしましょう。開始時間ギリギリに到着するとテストセンターの職員に注意されてしまいます。受付で身分証明書2点の確認や署名、写真撮影などの手続きがあるため到着してすぐには受験できません。
・受験後
試験が終了するとすぐ合否とスコアが表示されます。その後職員にホワイトボードとペンを返却し、署名を記入してスコアレポートを受け取って終了になります。
3-3-2.オンラインで受験する場合
・受験前
30分前には試験開始の準備を済ませましょう。自身で行うセットアップや試験官によるチェックに時間がかかる可能性があるためです。
・受験後
画面の試験終了ボタンを押せばすぐ合否とスコアが表示され、試験官とコンタクトを取ることなく終了になります。
4.受験における注意点
受験する際に心得ておきたいポイントや注意点についてご紹介します。
4-1.試験における注意点
筆者が思う試験における注意点、問題の解き方などをご紹介します。
- 1問1分目安で解く
- 試験時間は90分あるので、見直し含めて2周できるくらいの余力を残しておく
- 消去法で解くと残った選択肢に集中して考えられるのでおすすめです
- 誤った選択肢のパターンとして以下2つがあります
①存在しないコマンドやオプションがある
②コマンドは正しいが、設問の意図と異なる - 迷う or 分からない問題には見直すフラグを立てておく。もしかしたらその後の問題でヒントになる文言が出てくるかもしれないです
4-2.受験環境における注意点
試験の申し込みをする際にオンライン(自宅)での受験かテストセンターでの受験にするか決める必要があります。テストセンターでの受験とオンラインでの受験は制約や環境が大きく異なるため注意点として下の表にまとめます。環境的にはテストセンターでの受験がベストだと思いますが、「光」などの専用線をひいている場合であればオンラインでの受験もありかなと思います。ご自身で移動時間や受験環境を考慮して受験環境を選択していただければと思います。
| テストセンター | オンライン | |
| 試験中のお手洗い | 残り時間は止められないが離席が許可されている。 | 離席したい時は試験終了となる。 |
| 試験中のメモ | 試験開始時ホワイトボードとペンが渡される。試験終了時に回収となる。 | オンラインホワイトボードが使用できるがメモできる量はネットワーク環境に大きく依存する。 |
| 通信環境 | 画面遷移は早い。 | Wi-Fi(70Mbpsくらい)だとかなり動作が重く画面遷移に時間がかかる。 |
| 目線 | 隣席を覗き込むような行為は許容されないが多少下や上を向くことは可能。 | パソコンから目線を外すとポリシー違反になり、繰り返すと強制的に試験終了になる恐れがある。 |
5.最後に
先日、たまたまベテランのインフラエンジニアの方と話す機会があったのですが、「クラウド(AWS EC2)は簡単にデプロイができるので、基となっているLinux技術は軽視されがちだが、やはりインフラエンジニアならLPICレベル2くらいの知識は何かと応用がきくので持っていて欲しい。」との意見を伺いました。私もトラブルシューティングなどはベースの知識が必要になってくるので、全くもってその通りだな。と思いました。LPICレベル2はレベル1の内容を深掘りしたような内容なので、LPI資格の中で一つの区切りになっています。なので、レベル2相当の知識が現場における最低限のラインだと思っていただいてもいいのかもしれません。是非皆さんもLinux資格の中でも最もポピュラーなLPICの資格をレベル1から取得することでエンジニアとしてのバリューを高め仕事の自由度や生産性を高めていける手段として活用していただきたいと思います。本記事が皆様の参考になれば幸いです。

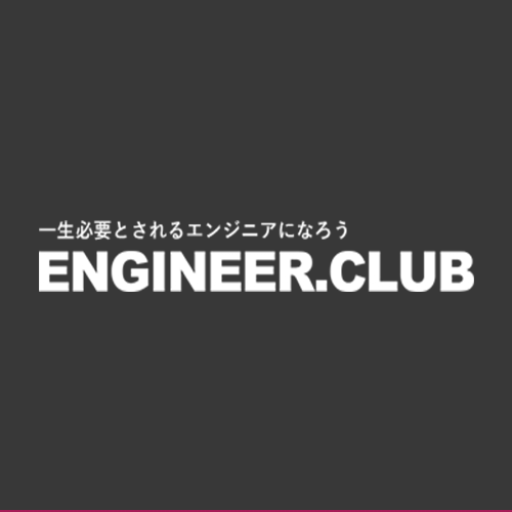

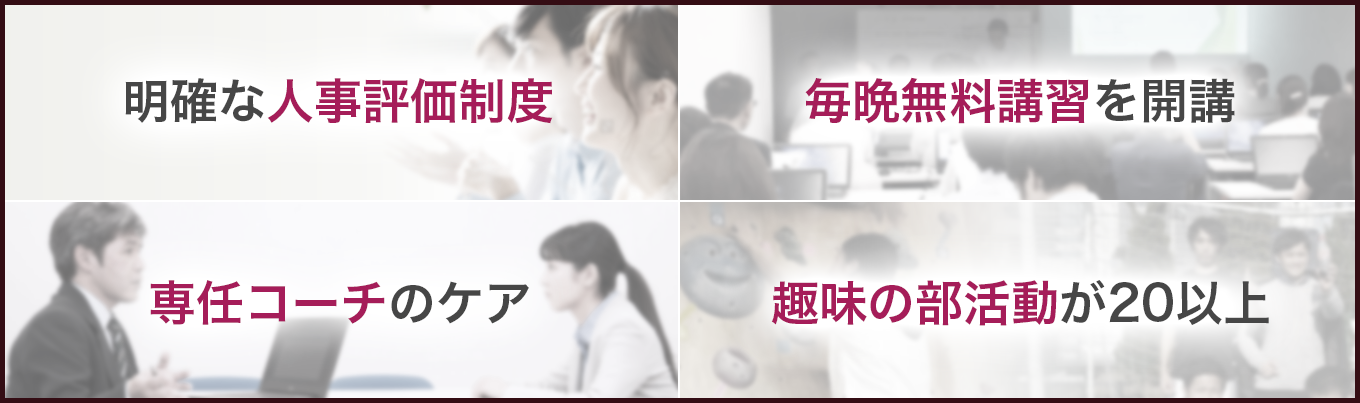
コメント