
エンジニアに会計知識は必要か?会計の知識習得をおすすめする理由
ITエンジニアにはプログラミング以外にも、現場によって様々な業務知識が求められます。「会計」もその中のひとつです。エンジニアに必要な「会計」は、必ずしも簿記の専門的な知識の深掘りを指していません。どちらかというと、会計の基礎的な知識をベースとして次の2点ができることを指します。
- お客様と会計業務の会話ができること
- 会計システムの仕様や扱い方に精通すること
世の中にある会社の数だけ、会計の仕事があります。エンジニアが「会計」の知識を求められる現場に立たされることがあったとしても珍しい話ではありません。
この記事ではITエンジニアに「会計」の知識習得をおすすめしており、その理由について述べております。キャリアプランに迷われている方へ、みな様の選択肢を一つでも増やすことができたら幸いに思います。
目次
1.エンジニアに会計の知識習得をおすすめする理由
ITエンジニアには会計の知識が必要と耳にすることがありますが、実際はどうなのでしょうか。
長年エンジニアとして様々なシステムを扱ってきた私の経験上、答えは「必ずしも必要ではないが、出来ればあったほうがよい」です。第1章ではその理由を解説いたします。
1-1.会計システムを支えるエンジニアはニーズがあるから
デジタル化された現代では、多くの顧客が会計システムを導入しています。会計システムを開発したSIerだけではとてもそれらの顧客に対応することはできません。そのため、数多くのSIerが協力して世の中の会計システムを支えているのが実情です。
実際、現場ではエンジニアが不足しています。とある会計システムを開発したSIerでは、新卒でもかなり高額な年収を用意して人材確保に努めているほどです。大手SIerでも、業務の一環として他社の会計システムを扱っていることが珍しくありません。私が新卒で入社した時の会社も、社員の半数が会計システムの業務を行い、半数はその他公共系、インフラ系、といった感じでした。
ITエンジニアには35歳限界説というものがありますが、会計システムの現場では35歳を超えて活躍されている方も珍しくありません。これも、エンジニアへのニーズが高いことを物語っているように考えます。
なお、世の中には会計の知識がなくともご活躍されておられるエンジニアの方も数多くいらっしゃいます。どうしてもエンジニアには会計が必要だという話ではございませんので、誤解のないように補足させていただきます。
1-2.主要な業務は会計とつながっているから
ITエンジニアは大別すると3つに分かれます。
- 業務系エンジニア
- WEB系エンジニア
- 組み込み系エンジニア
このうちの業務系エンジニアが、会計の知識を必要とする場面に多く遭遇します。なお業務系エンジニアとは、企業の特定の業務をIT化するエンジニアのことをいいます。
業務系エンジニアがIT化する企業の主要な業務には、必ずお金が絡みます。そして、そうしたお金の流れを記録していくことが会計業務の基本にあります。つまりすべての主要な業務は会計と必ずつながっていることとなります。
とある八百屋さんの例で考えてみましょう。この八百屋さんは毎朝近くの農家から野菜を仕入れています。そしてパートのおばちゃんが野菜を並べて、お客様に売っています。農家から野菜を仕入れる時にお金がかかります。お客様に野菜を売った時にお金が入ってきます。野菜を販売・管理するおばちゃんに人件費がかかります。
たとえば、この八百屋さんの業務をシステム化するとします。どんな業務管理システムが必要になるでしょうか。
- 購買管理システムで、毎日農家からいくつ野菜を仕入れているのか、仕入れ値はいくらかなどを管理する。
- 販売管理システムで、毎日どの野菜が何個売れたのか、売り上げはいくらかを管理する。
- 人事給与管理システムで、従業員の住所はどこか、パート代はいくらかなどを管理する。
- 会計システムで、日々のお金の流れを記録する。
八百屋さんがここまでシステマチックにすることはあまり無いと思いますが、少し空想しただけでこれだけの業務をシステム化することが可能です。そして、すべての業務管理のお金のやり取りは最終的に会計システムに連携する必要があります。
いくつ仕入れて、いくつ売って、人件費がいくらかかって、そうした情報をもとに赤字か黒字かが算出されて、国に納める税金の額も決まります。それらは会計に必要な情報なのです。
なお、業務系エンジニアに限らず、WEB系、組み込み系エンジニアでも会計の知識を習得して損はありません。ビジネスリテラシーの高いエンジニアになれるからです。上述のとおり、会社員が行う主要な業務はすべて会計につながっています。上の立場になるほど、会社の利益を意識した会話が増えてきます。会計抜きに会話がしづらくなってくるということです。
1-3.会計システムは基幹システムの主人公だから
基幹システムとは八百屋さんの例でいうと、「人事管理システム」「購買管理システム」「販売管理システム」「会計システム」すべてを指します。基幹システムについて明確な定義はないようですが、要するに会社の主要な業務を管理するシステム群と考えてよいかと思います。
会計システムがこの基幹システムの主人公という話は、すでにご納得いただけるかと思います。人事管理システムにしろ、購買管理システムにしろ、販売管理システムにしろ、すべて会計システムとつながっているからです。
たとえばあなたの担当する業務管理システムが人事給与管理システムだったとします。人事給与管理システムでは下記のお金のやり取りが発生します。
- 給与賞与
- 旅費交通費
- 従業員貸付金
- 立て替え払い
etc・・・
これらの金額を会計システム側に連携する必要があります。その時に何を考慮する必要があるでしょうか。
- 役員報酬などを会計の科目に合わせて再集計する必要があるか?
- 全社員を集計した金額でいいのか、それとも部署ごとに分けて集計か?
- どのタイミングで連携したらよいのか?
etc・・・
会計を意識しながら、こういったことをお客様と詰める必要が生じるでしょう。
つまり基幹システムを構築する場合、どの業務管理システムを担当するにしても、会計システムを意識せざるを得ないということになります。逆にいうと、会計の知識は基幹システムのどれを担当しても役に立つということです。
なお補足ですが、基幹システム以外のシステムでは会計に出番が回ってくることはほとんどなくなります。たとえば、八百屋さんの宣伝用の「ホームページ」を作成するケースを考えてみましょう。
「ホームページ」は安売りの開催等を告知するだけの用途で使用されるものとします。無くても八百屋さんの本来の業務に大きな支障はありません。基幹システムの定義からは外れることになり、会計の出番もありません。
想像してみてください。
この八百屋さんの宣伝用ホームページ作成に会計の知識が必要になることは、まず無さそうですよね。
2.エンジニアにおすすめする会計の勉強方法
では、会計知識を身に付けるにはどうしたらよいのでしょうか。私は日商簿記3級の資格取得をおすすめします。第2章では日商簿記3級をお勧めする理由について解説いたします。
2-1.資格制度を利用して知識を身に付けよう
日商簿記3級は、簿記試験の中でも難易度のやさしい資格です。よく世間では日商簿記2級から履歴書に書くことができるといわれます。しかしまずはあせらずに3級からチャレンジしましょう。担当する業務によっては、3級で十分なことも多いです。日商簿記3級を学ぶことで、以下のことが期待できます。
- 会計で使われる仕分けの仕組みについて、ある程度理解できる
- 会計で使われる勘定科目等の独特な用語について、ある程度理解できる
- 会計の重要な目的の一つである財務諸表作成までの流れについて、ある程度理解できる
会計ではたくさんの勘定科目が登場します。
- 「前受金」
- 「前渡金」
- 「売掛金」
- 「買掛金」
etc・・・
これらの勘定科目がどのように使われているのか。財務諸表の中でどのような意味を持っているのか。そもそも財務諸表とは何者か。お客様と会話する時にはこれらの会計の用語が飛び交う事になるでしょう。
また、開発・運用・保守の現場においても会計を理解していることはシステム仕様の理解につながるのでとても重要です。プログラム能力が多少見劣りしていても(あるいはなくても)、会計とシステム仕様を理解していることで重用してもらえることもあるくらいです。まずは日商簿記3級を取得して、必要に応じて上級資格にチャレンジすることをおすすめします。
3.エンジニアにおすすめする会計が学べる本3選
エンジニアとして、より実践的な知識を身に付けたい方にはエンジニア向けに会計を解説した本があります。資格取得で会計を体系的に学ぶのと並行して、これからお勧めする本を読むことでより知識が実務と有機的につながってくるはずです。第3章では、私がお勧めする本3選をご紹介いたします。
3-1.エンジニアが学ぶ会計システムの「知識」と「技術」
ダントツでおすすめしたいのがこちらです。エンジニア向けに会計と会計システムを解説した良書です。このような内容が解説されています。
- エンジニアが会計システムを扱ううえで必要な会計基礎知識の解説
- 会計システムでどのように会計が実現されているかの仕組みを解説
- 周辺業務システムと会計システムの関係を解説
- 会計システム構築プロジェクトの進め方、運用保守の実態について解説
- 会計システムの今後のトレンドについて解説
会計システムを扱うためにエンジニアが学ぶべきことが一通り網羅されているように思います。会計知識とシステムの仕組みを紐づけて解説してくれているので、非常にわかりやすいです。会計システムにはどんなマスタが必要になるか、どんな連携が必要になるのか、会計システム構築のリスクは何か。エンジニアを経験された方が執筆に加わっているので、まるで現場の空気感が伝わってくるようです。これ1冊読むだけでも十分に思えるくらい、充実した内容です。
3-2.ITエンジニアのための”業務知識”がわかる本
より業務知識に特化しているのがこちらの本です。主に上流のエンジニアが読むべき本かと思います。なおITエンジニアの公的な資格試験(ITパスポート、基本情報処理技術者試験等)でも、ストラテジ系の知識が問われます。そうした試験の対策にもなります。版を重ねること第5版。筆者の方の読者への思いがつまったベストセラーです。
3-3.ITエンジニアとして生き残るための会計の知識
こちらもITエンジニア向けに会計の知識を解説した本です。現代のビジネス3大スキルは「語学」「IT」「会計」といわれます。じつは「会計」は、3大スキルのひとつなのです。
しかしITエンジニアはこの中で特に「会計」のスキルと馴染みが薄い状況といわれるそうです。そのような状況を踏まえてエンジニア向けに会計の知識習得を目的として書かれた本です。
4.(会計システムにおける)経理担当とエンジニアで違う会計知識の使い方
私は昔、経理の仕事をしていたことがあります。会計については、実務をこなせる程度の知識が備わっていました。第4章では、そんな私が会計システムの現場に入って感じた、経理担当とエンジニアの会計知識の使い方の違いについて解説します。
4-1.経理担当者はシステムをどう使うか
経理担当者が会計システムを使って実現したいことは何でしょうか。お金の流れや取引を記録して、最後に財務諸表を作成することです。そのために経理担当者は、会計システムの基本的な使い方を理解する必要があります。
正確な会計処理のために会計システムをどのように扱えばよいか。または、会計システムの機能をどのように活用したら、会計業務が効率化できるかということを考えます。
- 繰り返し発生する日々の入力業務をテンプレート化できないか
- 消費税の端数処理の設定はどこで行うか
- 外貨のレートはどこで登録したらよいか
- 他の業務システムとどのように連携したらよいか
etc・・・
経理担当者は、会計システムをどう使ったら、自分のやるべき会計の業務が実現できるか、効率化できるかという視点を持ちます。会計システムの使い方を理解して利用する際に会計の知識を活用することとなります。
4-2.エンジニアはシステムをどう作るか
一方エンジニアは、会計をシステムで実現するためにどういう機能が必要か、どうしたらより効率的な業務が可能になるかということを考えます。
- 日々繰り返されるような入力業務についてはテンプレートをマスタに登録できるようにしよう
- 消費税では端数処理が必要なケースがあるので、端数処理の方法を設定する画面を用意しよう
- 外貨レートを管理するマスタを用意し、レートを自動更新出来る仕組みを作ろう
- 他業務からデータ連携するために、csvデータを取り込める機能を用意しよう
etc・・・
会計を全く知らないで、こうした考慮を漏らさずにシステムを作ることができるでしょうか。また、お客様と会話できるでしょうか。エンジニアは、どういう仕組みで会計システムを作ったら、お客様の会計の業務が実現できるか、効率化出来るかという視点を持ちます。会計システムで必要な機能を理解して開発する際に会計の知識を活用する事となります。
5.さいごに
冒頭に申し上げた通り、エンジニアに会計の知識は必ずしも必要ではありません。実際会計を意識せずに対応可能な現場はいくらでもあります。会計システムの開発現場でさえも、担当箇所によっては会計の用語が出てこないこともよくあります。
しかし会計に熟知し、会計システムの扱いに長けたエンジニアは、上流でも下流でも重宝されているのもまた事実です。そして「会計」はニッチなスキルではありません。身に付ければ、どこでも活かせる汎用性の高いスキルです。会計の現場以外で活躍しているエンジニアは、会計の代わりにその現場で必要な知識をキャッチアップしているはずです。
果たしてそれは、その現場以外でも使える知識でしょうか?
プロジェクトが終わって他の現場に移った時に、活かせる知識なのでしょうか?
会計は、活かせます。
会計の仕事は、いくらでもあるからです。希望すれば次も会計のプロジェクトに就ける可能性がいくらでもあります。
キャリア形成に迷われている方へ。この記事では特に会計にフォーカスをあてて、エンジニアが身に付けておきたいスキルの一例としてご紹介しました。エンジニアを優位にするのは決して会計だけではありません。会計に限らず、専門的な知識を持つことでエンジニアの優位性はかなり高くなります。会計はあくまでその中の一つにすぎません。
しかし、どの業種でも使われるため、活躍の場を広げられるスキルなのでおすすめしました。皆様のキャリア形成の参考になれば幸いです。

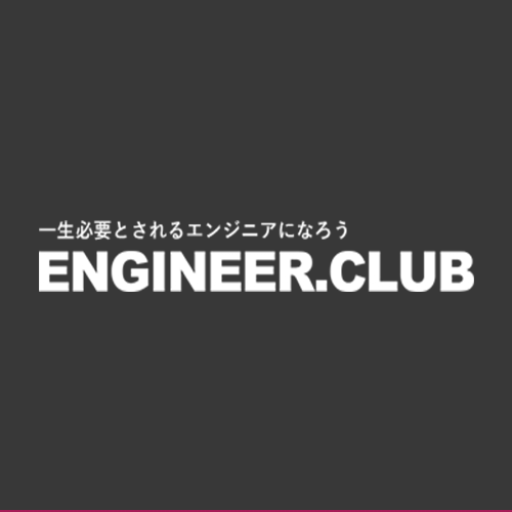

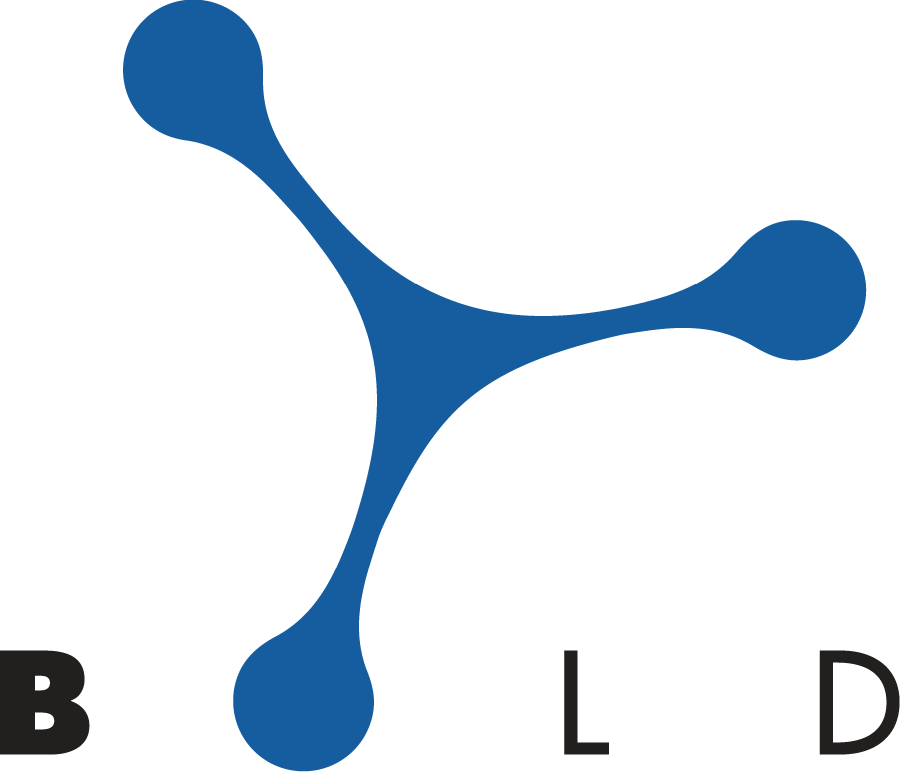
コメント