
Microsoft Certified Azure Administrator Associateとは?
近年、サーバーエンジニアであれば、誰もが耳にする「クラウド」。
クラウドサービスにおいて、Microsoft 社が提供する「Microsoft Azure」に携わっている方も多いかと思います。
また、「Microsoft Azure」に関連する認定試験も存在し、「難易度:中級」かつ「サーバーエンジニア(サーバーインフラ業務系)」向けの認定資格が「Microsoft Certified Azure Administrator Associate」となります。
筆者も2022年12月にこの資格試験を受験し、無事、合格できました。
今回、この資格を取得するために取り組んだ「計画」→「実践」について記載いたしますので、皆さんの一助となれば幸いです。
目次
1.Microsoft Certified Azure Administrator Associate とは
Microsoft社が実施する認定資格試験の1つで、Microsoft Azure認定試験の中で中級者向け試験となります。主にAzureインフラ業務における管理者・技術者を目指す方向けの資格であり、Azure環境におけるオペレーティング システム、ネットワーク、サーバー、仮想化の知識を要求されます。
2.Microsoft Certified Azure Administrator Associate 試験合格のために ~計画編~
2-1.受験日を早めに決定
モチベーションを保ちながら学習できるよう、受験日を早めに決めておくことが大切です。筆者は、「学習開始日より2ヶ月後」を目標とし、学習開始から2週間程経過した後、試験申し込みを行いました。この期間で試験の難易度をある程度予測することができ、限られた時間で効率よく学習しようと考えたためです。尚、筆者の過去の経験によるものですが、「学習を進めて行き、試験合格の自信が持ててから受験申し込みをしよう」というスタンスで学習を進めても受験予定日がどんどん先延ばし(場合によっては受験もせずに終了)になりかねません。「受験日を先に決め、試験申し込みをなるべく早めに行う」が大切です。
2-2.目標点数を設定
試験合格点が700点(満点は1000点)ですが、筆者は「800点~850点」を目標とし、学習を進めました。ボーダーラインと満点の中間くらいを目指すことで試験当日、不安やプレッシャーを感じずに望めると判断したためです。尚、筆者はこのスタンスで進めたことにより、試験当日、「わかる問題は確実に解いていく」、わからない問題は慌てず後回しにする」という取捨選択が冷静にできたと実感しています。
2-3.参考書を選定
「合格対策 Microsoft認定試験 AZ-104:Microsoft Azure Administratorテキスト&問題集」を使用しました。試験合格に必要なキーワードや要点に関する記載内容がわかりやすいこと、Microsoft Azure認定試験初級者向け資格である「Microsoft Certified Azure Fundamentals」を取得した時の経験より、同一著者・出版社の参考書が学習しやすいと判断したためです。
2-4.本試験を意識した対策(模擬試験を選定)
「Udemy」を選びました。有料ですが、1度購入すれば、無期限で繰り返し学習できること、本試験に類似した問題が多数出題されること、各問題の解説が丁寧であるため、この問題で繰り返し学習し、解説まできちんと理解できれば本試験も確実に合格できること、そして、Microsoft Azure認定試験初級者向け資格である「Microsoft Certified Azure Fundamentals」を取得した時の経験より信頼できると判断しました。また、スマートフォンでも学習できるため、通勤の合間に効率よく学習することが可能です。
https://www.udemy.com/course/az-104azure-administrator-associate/
2-5.1日あたりの学習時間を決定
毎日コツコツと学習することが大切です。筆者は「30分~1時間」を目安としました。尚、試験直前の追い込みにおいては、「2時間~3時間」を目安に計画しました。尚、学習時間決定にあたり「2-1. 受験日を早めに決定」に記載した「モチベーションを保ちながら学習できるよう、受験日を早めに決めておく」の意識が大切です。これを行うことで1日当たりの学習時間がコントロールできるようになると思います。
3.Microsoft Certified Azure Administrator Associate 試験合格のために ~実践編~
3-1.参考書を使用した学習について
「2-3. 参考書を選定」で紹介した参考書を約1ヶ月間、繰り返し読み込みました。参考書を使用した学習の理解力・暗記力は、個人差があると思います。筆者は、暗記力が優れていないため、数回(7~8回)読み込み、暗記要素の項目において本試験で不安とならないよう、意識して学習しました。筆者の体験談ですが、当該参考書をしっかりと頭にたたきこむことで、「本試験における問題文の細かい情報をきちんと理解・判断した上で回答する」につながりました。
3-2.本試験を意識した学習について
「2-4. 本試験を意識した対策(模擬試験を選定)」で紹介した「Udemy」による模擬試験を約1ヶ月間、繰り返し実施しました。模擬試験の正答率はほぼ、100%とすること、模擬試験の解説をきちんと理解すること、模擬試験及び解説より「本試験でこんなパターンの問題が主題されるかも」を意識して学習しました。筆者の体験談ですが、当該模擬試験の内、40%~50%は同一問題または類似問題が主題されました。「学習時間をあまり確保できないけど、最短で合格したい」という方は当該模擬試験で繰り返し学習し、正答率を100%にすれば、なんとか合格可能できるかもと思うくらい質が高いです。
3-3.総仕上げ
模擬試験での学習をメインとし、模擬試験で出てくる各用語を参考書で再度、確認するという流れで進めました。とにかく反復して「模擬試験実施→各用語を参考書でチェック」を行い、本試験で自信が持てるよう、取り組みました。筆者の体験談ですが、「模擬試験で問題慣れしておくことで本試験も落ち着いて望めた」と実感しております。
4.Microsoft Certified Azure Administrator Associate 試験合格のために ~試験直前及び試験当日~
4-1.試験直前に確認すべきこと
(1)試験詳細について
本試験は問題形式が3フェーズに分かれております。①問題文に対して正しい答えを1つまたは複数選択する形式。②問題文の内容正しいか否か「はい」か「いいえ」で回答する形式。③長文読解(架空企業のケーススタディに関する問題)が示され、これについて数問出題及び回答する形式。注意点は、①及び③については、次フェーズに進む前に問題の見直し及び回答修正は実施できるが、次フェーズに進むと問題の見直し及び回答修正ができなくなること、②については、1度回答したら見直し及び回答修正が一切行えないことの2点です。
(2)長文読解(架空企業のケーススタディに関する問題)について
「2-4. 本試験を意識した対策(模擬試験を選定)」で紹介した模擬試験(Udemy)にも長文読解(架空企業のケーススタディに関する問題)が何問か用意されておりますが、このタイプの問題を試験直前に再確認することを強くお薦めします。逆にこのタイプの問題を事前に抑えておかないと、試験当日に慌てることになりかねないです。
(3)試験経験者のコメント、アドバイスを確認
インターネットで本試験経験者のコメント、アドバイスを試験直前に確認することをお薦めします。経験者のコメント、アドバイスを確認することで、試験直前で再度、重点的に学習すべきことや試験当日に対する事前イメージが行えると思います。
4-2.試験当日に注意すべきこと
「問題数と時間配分」に注意してください。試験開始前の説明で問題数と試験時間が表示されますが、これらは多少変動があるようです。ただ、「4-1. 試験直前に確認すべきこと – (1) 試験詳細について」で記載した問題形式①~③において、問題形式②、③はそれぞれ5問前後出題され、残りは全て問題形式①となります。この点を抑え、試験当日の時間配分をコントロールして頂ければと思います。
5.さいごに
「2-3. 参考書を選定」で紹介した以外の参考書がいくつかありますが、自身の好みに合う参考書を選んで頂いても問題無いと思います。ただ、参考書は1冊で充分だと思います。1冊の参考書で繰り返し学習することを心がけて頂ければと思います。また、「2-4. 本試験を意識した対策(模擬試験を選定)」で紹介した模擬試験(Udemy)は強くお薦めしますが(「3-2. 本試験を意識した学習について」にも記載しておりますが、40%~50%は同一問題または類似問題が主題されました)、より確実な合格を目指したい場合、もう1種類別の模擬試験を活用しても良いと思います。参考書のみで本試験に望むと予想外の問題で戸惑うと思います。筆者が本記事で紹介した参考書及び模擬試験がベストと断言することはできませんが、「参考書及び模擬試験の両方で学習する」ことが本試験対策としてベストと考えております。学習における費用負担が少し多くなりますが、確実に資格を取得するため、ぜひ、この組み合わせで取り組んで頂きたいです。



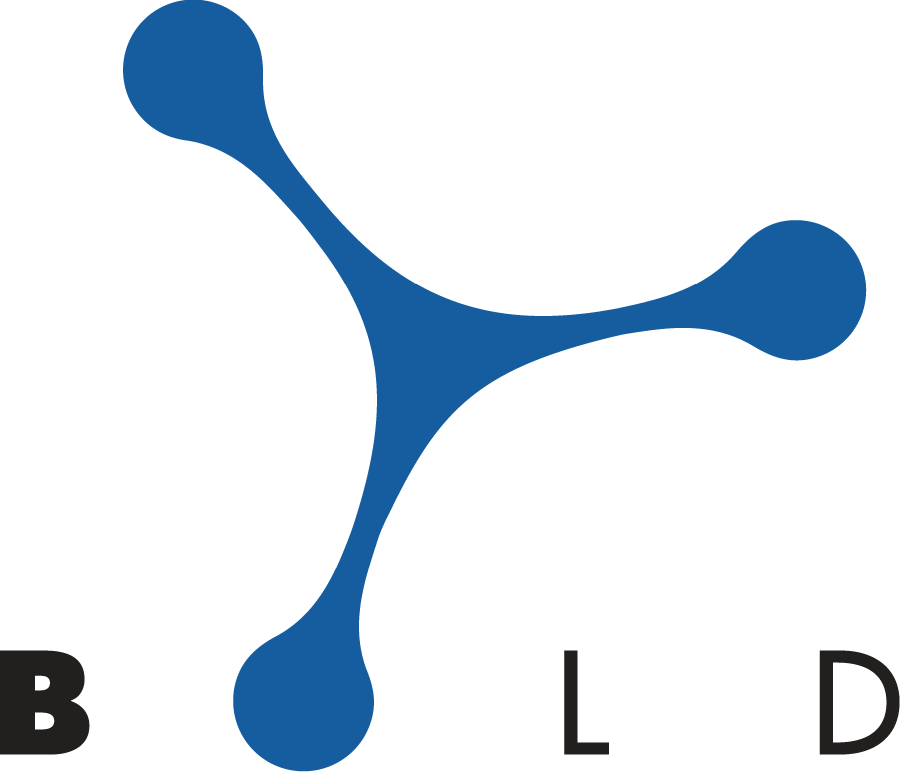
コメント